久々の映画音楽ネタになります。
今回は80年代映画の中から筆者のオススメ、「これぞ、80年の音」という感じの曲をチョイスしました。
80年代は大衆向けの映画がヒットした背景もあって、青春ものに偏ってしまった感が否めません。
『初体験/リッジモント・ハイ』
(原題:Fast Times At Ridgemont High)1982年
監督:エイミー・ヘッカーリング
出演:ジェニファー・ジェイソン・リー、フィービー・ケイツ 、
ショーン・ペン 、ジャッジ・ラインホルド
キャメロン・クロウが脚本を書いたドタバタ青春ものです。初めてショーン・ペンを知ったのが本作でした。
フィービー・ケイツのセクシーなシーンが話題になりました。ジャッジ・ラインホルド、エリック・ストルツなども出演しています。
フィービー・ケイツ人気に気をよくして、翌年には彼女主演で「プライベートスクール」が公開…イヤらしくないセクシーな彼女。クリンとした目がキュートでしたものね〜
Somebody's Baby - Jackson Browne
『フラッシュダンス』
(原題:Flashdance) 1983年
監督:エイドリアン・ライン出演:ジェニファー・ビールス 、マイケル・ヌーリー
製鉄所で働きながらダンサーをめざす女の子のサクセスストーリーです。
アイリーン・キャラの「What A Feeling 」は、有名すぎるのでこちらに…といってもこの曲も結構世に知れ渡ってるかな。
こういう軽ぅーい感じのシンセサイザーの音は80年代って感じです。
エイドリアン・ラインって、こうしてみると結構頑張ってヒット作生み出してたんですよね。
Maniac - by Michael Sembello
『ビバリーヒルズ・コップ』
(原題:Beverly Hills Cop) 1984年
監督:マーティン・ブレスト出演:エディ・マーフィ、リサ・アイルバッハー、ジャッジ・ラインホルド
幼なじみを殺害された黒人刑事アクセル。彼は上司の反対を押し切って、真相を暴くためロスへやって来る。そして現地の二人組の白人刑事を味方につけ、悪の組織を叩きつぶす……。(allcinemaより)
グレン・フライの「The Heat is on」をはじめ、アルバム自体が大ヒットしましたね。 今回は、軽快なメイン・テーマの方を!
Axel F - Harold Faltermeyer
『カリブの熱い夜』
(原題:Against All Odds)1984年
監督:テイラー・ハックフォード
出演:ジェフ・ブリッジス、レイチェル・ウォード、ジェームズ・ウッズ
1930年~60年代にかけて活躍したジャック・ターナー監督の「過去を逃れて - Out of the Past(1947年)」のリメイク。(最近知りました。)
「愛と青春の旅立ち」「ホワイトナイツ/白夜」のテイラー・ハックフォードがメガホンを取っています。
ひとりの美女を巡って2人の男たちが、死闘をくりひろげる。
ジェフ・ブリッジスがまだ脂ぎっていた…当時は嫌いでした。
作品自体は、少し間延びしてしまった感がありました。スリリングな見せ場はあるのですが、もう少し凝縮してほしかったかな…名優をそろえたんだからさ。
レイチェル・ウォードがそれはそれはお美しい!
この曲は、説明はいらない(と思う...若い人は知らないかも)名曲です。リリー・コリンズのお父様といった説明が分かりやすいですね。
ジェネシスのドラマーだったフィル・コリンズがソロになってヒットを飛ばした中の1曲です。
Against all odds - Phil Collins
『ビジョン・クエスト 青春の賭け』
(原題:Vision Quest)1985年
監督:ハロルド・ベッカー
出演:マシュー・モディーン、リンダ・フィオレンティーノ、マイケル・シューフリング
アマチュア・レスリングのチャンピオンを目指す18才の少年の日々を、年上の女性への恋などを絡めながら綴った青春ドラマ。
(allcinemaより)
サウンドトラックには、マドンナの曲が2曲入っています。スタイル・カウンシルの「Shout To The Top」は、スタカンのアルバム「Our Favorite shop」にも収録されています。
ポール・ウェラーがノリに乗っている時期だよね~。
Gambler - Madonna
Shout To The Top - The Style Council
『ナインハーフ』
(原題:NINE 1/2 WEEKS) 1986年
監督: エイドリアン・ライン
出演:ミッキー・ローク、キム・ベイシンガー
80年代が生み出したヤッピーという人種をミッキー・ロークが演じています。
感想をアップしていますので、詳細はこちらを…
デュラン・デュランのイケメンベーシスト、ジョン・テイラーがサントラに参加。デュラン×2とはひと味違った曲に仕上がっています。
I Do What I Do - John Taylor
うーん、ジャンル的にみるとかなり偏ったかもしれませんが、懲りずに後編も引き続きアップします。


にほんブログ村
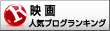
映画 ブログランキングへ
















































