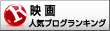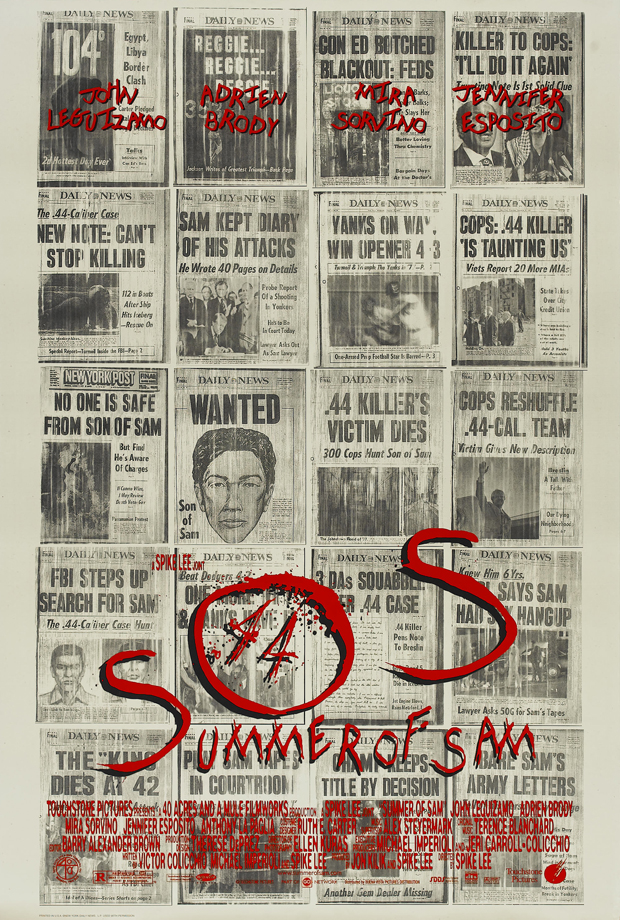2015年、新しい年が明けました。
遅ればせながら明けましておめでとうございます!
仕事の合間に観た映画の感想を今年もちまちまとupしていく所存ですので、宜しくお願いいたします。
さて、本年初の感想は2月20日に全国公開される「きっと、星のせいじゃない。(The Fault in our stars)」を観賞しました。
お涙頂戴映画かなって印象だったので、最初はイマイチ気乗りしなかったのに突如360度転換!(ん…?! )気が変わりまして、やっぱ観てみようかなぁと。。。
お話は末期がん患者同士が出会いやがて恋に落ちる…ここまできいただけだと、ちょっと通な方だと「ケッ!!」って鼻で嗤うかも知れないですねぇーーー。
ストーリー
ステージ4の甲状腺ガン末期患者ながらも、抗がん剤の効果で深刻な状態を免れているヘイゼル(シャイリーン・ウッドリー)は、学校にも通えず、友人もできず、酸素ボンべなしでは生活できない女の子。そんなある日、ガン患者の集会で骨肉腫を克服したガス(アンセル・エルゴート)と出会う。ヘイゼルに惹(ひ)かれたガスだが、ヘイゼルは彼と距離を置いてしまう。ヘイゼルの気を惹こうと、彼女の愛読書の著者 ヴァン・ホーテン(ウィレム・デフォー)にメールを送って返信をもらうことに成功するガス。その後、二人は作家に会おうとオランダへ旅行に出る……。
キャスト
シャイリーン・ウッドリー - ヘイゼル・グレイス・ランカスター
アンセル・エルゴート - オーガスタス・ウォルターズ
ナット・ウルフ - アイザック、オーガスタスの親友
ローラ・ダーン - フラニー・ランカスター、ヘイゼルの母親
サム・トランメル - マイケル・ランカスター、ヘイゼルの父親
リリー・ケンナ - 幼少時のヘイゼル
ウィレム・デフォー - ピーター・ヴァン・ホーテン
ロッテ・ファービーク - ルドウィグ・ヴリーゲンサート、ヴァン・ホーテンのアシスタント
スタッフ・作品情報
監督: ジョシュ・ブーン
脚本: スコット・ノイスタッター マイケル・H・ウェバー
原作 : ジョン・グリーン『さよならを待つふたりのために』
製作: ウィック・ゴッドフリー マーティ・ボーウェン
音楽: マイク・モーギス ネイト・ウォルコット
撮影: ベン・リチャードソン
編集: ロブ・サリヴァン
配給: 20世紀FOX
公開: 2014年6月6日(アメリカ合衆国)
日本公開: 2015年2月20日
原題: The Fault in Our Stars
脚本のスコット・ノイスタッターとマイケル・H・ウェバーは「(500)日のサマー」のコンビ。そういうワケでおのずとポップで軽快な映画を想像してしまいます。
自分が死んだ後の世界が心配で仕方ない女の子ヘイゼルと死んだ後に人々に忘れられてしまうことが恐くて仕方ない男の子ガスが出会います。
もちろん、ガン(しかも末期ガン)と向き合う若い男女の話なのでどうしても泣きます、泣かされます。
ただ、それだけの映画ではなくて彼らがあまりに自虐的で笑ってしまうところや「年齢にしては大人だよなぁーー」って感心したり、ほのぼのしたり。
最初は観る目線は当然のごとく上から目線です、親目線。主人公 ヘイゼル・グレイス・ランカスターの母親役はデヴィッド・リンチ作品でおなじみのいつも苦しんでいるような表情のローラ・ダーン。
彼女もこんな年頃の娘の母親役だよなーってやけに感慨にふけってしまいました。母親役もめずらしいですね。
(初めて出会ったのが劇場に「ブルー・ベルベット」を観に行ったときですもの。なんか、やけにブサイクな女の子だものでずっと脳裏に焼き付いて離れなかったのです。ごめんなさい^^;;;)
で、話を元に戻すと
「(500)日のサマー」のテイストを醸し出しつつ、死に係るなにかグッとくるセリフをあちこちにちりばめた作品です。
「(500)日...」に通じるポップでかわいい演出も出てきます。(監督さんは全く別な監督さんなんですけれどね)
主演のヘイゼルには今やハリウッドの二大しゃがれ声女優(1人はジェニファー・ローレンス)の中の1人シャイリーン・ウッドリー。
オーガスタス・ウォルターズを演じるアンセル・エルゴートもキュートでした。「ダイバージェント」でシャイリーン・ウッドリーの兄の役で共演していましたね、印象が薄かったけど。よくみると上唇がアヒルみたいでかわいい♪
 ガス(オーガスタス)は火をつけないタバコを口にくわえるちょっとヘンな習慣を貫いている。「命を奪うものからその能力を奪う」というメタファーだと言い張り、ただのタバコをくわえる彼の姿はユーモラスで滑稽で愛らしく、切ない。青田赤道のキセルみたい。(例えが古い^^;)
ガス(オーガスタス)は火をつけないタバコを口にくわえるちょっとヘンな習慣を貫いている。「命を奪うものからその能力を奪う」というメタファーだと言い張り、ただのタバコをくわえる彼の姿はユーモラスで滑稽で愛らしく、切ない。青田赤道のキセルみたい。(例えが古い^^;)愛称がガスでいつもタバコをくわえていて、ラスト近くでガソリンスタンドでタバコを買いに行って体調が悪くなる…っていうとこも切ない中のユーモアなのかな。
自分がいなくなってしまった後の世界を心配しているヘイゼルが健気。「自分が死んだ後に両親はどうなっちゃうの?」って常に心配なんですね、彼女。
ある場面でとうとう涙、涙、、、土砂降りのように涙してしまいしてね、いやはや。。。声を上げて泣いてしまいそうだった^^;;;
ウィレム・デフォー演じる作家ヴァン・ホーテンのイヤなオヤジっぷりがこれまた素晴らしくシックリくる!
賞賛すべきクソオヤジ!!
ヴァン・ホーテンってココアみたいな名前の作家に会うために2人はオランダに出向く。彼の小説のラスト部分を知る旅、直接彼に質問するためだ。
原作本「さよならを待つふたりのために」は未読なので小説の内容はよくわからない。
想像するに、死に向かう2人に希望を与え、死というものを熟知する作家と話すことで安心すること、「死=真っ暗な世界ばかりではないこと」を確信したい、とにかくすがりつく術(すべ)だったのだろう。
病気が治るようなことはありえないのに、何かにしがみつき、ささやかな希望を無意識に抱いてしまうのは若くても年老いていても人間であれば同じだ。
私がブログタイトルで使用した“0と1の間の無限...”は劇中のヘイゼルが語るセリフで、これでもかっていうほど泣かす場面で使われています。
もとのタイトル「The Fault in Our Stars」の意味合いは、この作品の2/3ほどでみたところでわかってくる。
実は私はヘイゼルとガスが出会ったばかりの時にうっすらと気がついてしまいましたが、それについてはこの作品の出来を落とすわけではないのでさほど気にならない。
日本のタイトルが「きっと、星のせいじゃない。」と原題と真逆なとこ、なかなかもってよろし。
この世の中にはどう振る舞おうと、自分の力ではどうにもならないこともあるけれどそれに屈しない勇敢な若者もいるんだよ、それも人生である…そういう映画です。
ガスがヘイゼルに会ったばかりの時に「きみは『Vフォー・ヴェンデッタ』のナタリー・ポートマンに似てるね」って言うのだけど、彼女の凛とした表情がほんとにそんなカンジなんですね、私も同意見でした。
ついでに『Vフォー・ヴェンデッタ』も大好きな映画です、私。
今年公開される「ダイバージェント」の続編も楽しみですね。
音楽もよくてサウンドトラック買わざるを得ないなって考えてます。
ヘイゼルのお父さん役のサム・トランメルがカッコよかったです♥
映画の内容とは少し逸れて個人的な話になるけれど、高校くらいのころ親とか友達何人かに「死んだときに自分の意識はどこにいっちゃうの?」という意味合いのことをきいた覚えがあります。
川を渡って天国のような世界にいくとか天国はあるよって話でその時は少し安心したものです。
でも、少し経つと天国などは死ぬことの恐さを遠ざけるための気休めに誰かが作ったものだという結論になってしまい、意識がとぎれてその後は?と考えて恐くて恐くて仕方がなかった。
自分が病気で余命わずかとかいう状況でもないのにそんなことばかり考えていた若い時をふと思い出してしまいました。
今更ながら無駄に臆病に過ごした日々が莫迦らしく思えてきます。やっぱり病は気からですね。。。。
で、今あらためてホーキング博士の「死後の世界」についての言及を読むと再び気がめいってきましたorz
[ロイター]「天国も死後の世界もない」、英物理学者ホーキング氏が断言